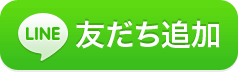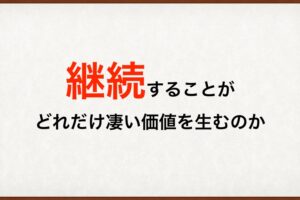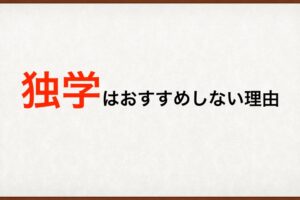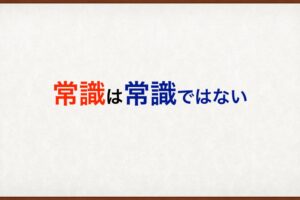「公務員=安泰」「消防士はやりがいのある仕事」
そう信じて目指す人は多いですが、実際に現場に立ってみると、理想と現実には大きなギャップがあることに気づく人も少なくありません。
この記事では、実際に消防士として働いた経験をもとに、「なぜ辞める決断に至ったのか」「辞めたあとの道には何があるのか」についてリアルな視点でお伝えします。
これから目指す人、今まさに悩んでいる人にとって、人生の選択を見つめ直すヒントになれば幸いです。
目次
消防士になるまでのプロセスと意外な実態
消防士になるには「公務員試験に合格しなければいけないから難しそう」と思われがちですが、実際はそこまで高い壁ではありません。
試験の内容と難易度
自治体によって異なりますが、一次試験では教養試験(一般知識・数的処理)、作文が主流でその倍率は2〜3倍ほどです。
次の二次試験では体力テスト(新体力テストなど)、面接が主流で、その倍率が4倍ほど。
国家公務員試験と比べると合格するのは現実的な難易度です。
僕はほぼ成績オール2の高校卒でしたが、短期集中で教養試験の過去問を回すことで、複数の自治体に合格できました。
合格のコツは「完璧主義を捨てること」・「準備をすること」
教養試験の得点源は「数的処理」と「文章理解」。苦手な科目を切り捨て、取れるところを確実に取ることで合格に近づけます。
加えて、体力試験では体力の総合点が評価基準となるので、長座体前屈や反復横跳びなど、点数が取れるところを確実に取れるようにしっかりと準備する。面接では協調性や社会性が問われるため、模範的な受け答えの準備をしておくと問題ないです。
公務員・消防士のイメージと現実とのギャップ

「公務員は安定している」「消防士はかっこいい」そんなイメージで目指す人も多いでしょう。
しかし、現実は思っているよりも過酷で、経済的にも精神的にも厳しい側面があります。
消防学校時代の手取りは約14万円でした。
現場配属後でも手取りは16〜18万円程度で、住宅手当や残業代が多少加算されても生活はギリギリ。
30代になっても大きな昇給は期待できず、「家族を養うには厳しい」と感じる人も多いです。
リストラの心配はない反面、「給与は年功序列」「副業禁止」「自由な働き方は選べない」など、現代的な働き方とはズレがあります。
30年後も同じ生活をしている自分を想像すると、不安に駆られる人も少なくありません。
現場で感じたストレスと現実的な悩み
消防士は命を守る責任のある仕事ですが、その分プレッシャーやストレスも大きいです。
勤務体制の過酷さ
基本的には24時間勤務→明け→休み、というシフト制(※2交代制は別)ですが、深夜でも出動があるため常に気を張っている状態です。
また、寝不足が続くことも珍しくなく、僕が働いていた職場では深夜の4時までは寝てはいけないといったルールがあり、体力的にもかなり厳しかったです。
上下関係と派閥文化
消防署は体育会系文化が根強く、先輩後輩の上下関係は絶対。
自分の意見が通りにくく、「空気を読む力」や「忖度」が重視されます。どれだけ真面目に努力していても協調性が苦手な人にとっては評価されにくい環境であり、かなりのストレス要因となります。
「理想と現実のギャップ」がモチベーションを奪う瞬間

「ヒーローのような仕事がしたい」と思って入った消防の世界。
でも、実際は掃除や訓練、事務作業が大半。「これって自分じゃなくてもできるよな…」という思いが募るたびに、モチベーションが落ちていきました。
「このままでいいのか」という疑問
20代後半になっても、給料は低く、成長実感も薄いまま。「このまま30年勤めて、定年後にやっと自由を得る人生でいいのか?」という疑問が日々大きくなっていきました。
辞める前に考えるべき3つの視点
消防士の経験は決してムダではありません。むしろ、民間企業や起業の場で活かせるスキルがたくさんあります。
- 現場対応力・冷静な判断力 → 災害対応や管理職に活かせる
- リーダーシップ・チームワーク → 営業やマネジメントに有利
- 公務員という信頼性 → 信用が必要な業界でも通用する
転職・起業・副業など、今は多様な選択肢があります。会社員をしながら副業で月5万円を稼ぐだけでも、精神的なゆとりは段違いです。

① 自分のスキル・強みの棚卸し:消防士時代に学んだリーダーシップや忍耐力、現場判断力は民間でも活かせます。それらを武器に何ができるか、何がしたいかを考える。
② 今辞めた場合の生活設計:退職金、貯金、副業など、経済的な下支えをどう作るか。
③ 家族や周囲への影響:辞める前に家族に相談し、理解を得ることはとても大切です。
なぜ今の時代に副業が必要なのか?

かつては「一つの会社に勤め続けていれば安心」と言われていた時代がありました。
しかし、今はその常識が大きく変わりつつあります。特に日本では、以下のような要因から「収入の多様化」が必須の時代に突入しています。
①日本経済が抱える3つのリスク
- 少子高齢化による社会保障の圧迫:働く世代が減り、年金制度の維持が困難になっています。
- 増税の加速:消費税や社会保険料の負担は今後も増える見込みです。
- 物価上昇(インフレ)と実質賃金の停滞:給料が増えなくても、生活コストは確実に上昇しています。
このような状況下で、「本業の収入だけで将来を支える」という考え方は、すでに現実的ではなくなっています。
②公務員の副業禁止と、見えないリスク
特に消防士をはじめとした公務員は、法律上副業が制限されているため、収入源を増やすことが難しい職業です。一見、安定して見える立場でも、以下のようなリスクを抱えています:
- 昇給スピードが遅く、収入の天井が早く来る
- 家族が増えると手取りでは生活が厳しくなる
- 定年後の再就職先が限られ、年金も不安
つまり、今のうちに「副業的なスキル」や「マネタイズの方法」を知っておくことが、将来への備えになるのです。
③副業はリスクの分散
副業とは「空いた時間で少しお金を稼ぐ手段」ではなく、自分の市場価値を上げる手段でもあります。
以下のような副業は、始めやすく、学びながらスキルアップが可能です。
- ブログ・アフィリエイト:情報発信力、ライティングスキルが身につく
- SNS運用:マーケティング思考と企画力が伸びる
- 動画編集:YouTube市場での需要が拡大中
- せどり・物販:仕入れ、販売、在庫管理など実務スキルを体得
これらはすべて、本業を辞めなくても始められるものばかり。
副業を通じて新しいスキルを身につければ、いざというときに本業に頼らない生き方が可能になります。
副業は今や「会社員の保険」とも言えます。特に20代〜30代のうちに準備を始めておくことが、将来の安心につながります。
少子高齢化・増税・年金不安など、今の日本では「1つの収入源だけでは将来が不安になる」というのが現実です。
特に公務員は副業が禁止されているため、本業以外の収入を作ることが難しい状況です。
まとめ|後悔しないための人生選択とアクションプラン

消防士は社会にとって非常に重要で誇り高い素晴らしい職業です。
しかし、全ての人に合っているわけではありません。また、現場で働く中で「理想と現実のギャップ」や「将来への不安」を感じる人も少なくありません。
その違和感を放置せず、立ち止まって考えることこそが、本当の意味で自分の人生に責任を持つということです。
-
-
- 消防士になるまでの道のりは、イメージよりも現実的で、誰にでもチャンスがある。
- 安定=安心ではない。収入の限界や人間関係など、長期的に見た課題も多い。
- 現場のリアルには、体力的・精神的負担が付きまとう。
- 辞めることは「逃げ」ではなく、「選択肢の一つ」。
- 消防士の経験は、転職・副業・起業に応用可能。
- 今の時代は複数の収入源を持つことがリスク回避に繋がる。
-
▽後悔しないための次のアクション
- 副業ブログなどから小さく副業を始めてみる
- 転職エージェントやスキルスクールで情報収集
- 消防士の経験を活かせる業種を調べる
- 僕のLINEから限定情報を学ぶ
人生は一度きり。20代・30代で気づけたのなら、それは大きなチャンスです。
今この瞬間の違和感や悩みを放置せず、行動に移すことが、後悔しない人生への第一歩になります。
電話相談やLINEでの指導も行っています。
少しでも現状に不満がある方はぜひ相談してみてください。